√
ルート(根号):根、根本、根源
〜人は一人きりで生まれてくる事を〜
これは遊佐未森のoneという曲の一節
まぁそうは言うけど、人間には必ず親があって
その親にも親があって
そうやって繋がってきた何かが自分に繋がってて
そしてそれを次へ繋げて
ドラマみたいな話だけれど意外と身近でもこういう話ってあるんだなぁということがあったので記録
当たり前の話だが私には両親がいる
そしてその両親にもそれぞれ両親があって、そのまた両親にも同様に
日本では本家、分家などという概念もあるが、これについてはひとまず横に置いておく
私が小さい頃(中学生以前だったと思う)父方の祖父がこういう話をしてくれたことがある
「おじいさんは養子だったんだよ
ある時、自分の戸籍を見ることがあって、その時におじいさんのお父さんに聞いたんだ
昔だから、囲炉裏のそばで火にあたりながらだった
『おやじ、俺って養子なのか?』
そうしたら親父は、目の前にある火箸をすっと抜いて、それで俺の頭を思いっきりバシッと殴ったんだ
それでおじいさんは思ったんだ
あぁ、これは2度と言ってはいけないんだって」
私の祖父の養父は、
「養子だろうが実子だろうがそんなことは関係ない
お前は俺の息子だ」
というメッセージを強烈な方法で伝えたのだろう
この話を聞いている時に、私の父がそこにいたがどうかははっきりと覚えてはいないが、
おそらくその場にいたことには間違いがないと思われる
その時の父がどういう顔をしていたかは覚えてないが、
記憶に残っていないということは、おそらく通常通りだったのだろう
父としては当然知っていることだったから、なんの反応もなかったのだろう
その父は、生前こんなことをよく言っていた
「俺は長男だからという理由で好きなことをさせてもらえなかった
ただ親父の言うがままに学校へ行って社会に出た
カズ(弟さん、私の叔父)はなんでも好きなことやってたのにな
俺も海軍(おそらく海自のこと)に行きたかった」
当時(父は昭和20年代生まれ)のことを考えれば、
家父長制の名残があるのは当たり前であり、
また祖父に従軍経験があることを考えれば、
いくら当時の花形とはいえ、大切な長男を軍隊(自衛隊?)にやって亡くすなんて絶対に避けたかったのだろう
そんな父が自身の経歴について一度だけ話してくれたことがある
(かなりセンシティブな内容につき注意)
「俺は一度東京に出たことがある
それも親父の紹介だったかなんだかだった
そこでは運転手みたいなことをしていた
だけれどある時、人を死なせてしまったんだ
そして俺はそこから逃げてきた」
この件については、この一度きりだった
今で言うところの「やんちゃ」では済まされないような悪行三昧を尽くしてきたのは知っていたが、
そんな過去があるとはその時まで知らなかった
この話を聞くまでは、父の生い立ちについて知っていることといえば
・気の弱い弟(2歳差)を庇って、いつも喧嘩ばかりしていた
・他校の奴らともよくやり合っていた
・バイクで峠を走っているときに転倒事故で長期入院し、留年した
というようなことばかりであり、実際に当時をよく知る人から裏も取っている
ちなみに父と私は同じ某私立の中高一貫校の卒業生である
私が在籍中でも、父の当時を知っている先生方がたくさんおり
「あぁ、お前がアイツの息子か」
とよく言われたものだ
最も父の方も、当時の保護者面談などで旧知の仲の方々と顔を合わせるたび
「アイツ(私の事)はお前に似なくて立派なやつだ」
とよく言われてたらしい
ザマァ見ろ
だが、この話があることによって、父の高校卒業後の足取りがある程度しっくりくるものとなる
私が知っている限りの古い記憶では、父は測量を生業としていた
この頃の父の居住地は、父の実家からは離れた田舎になる
何もかもを自身の父(私の祖父)の言う通りに従ってきたにしては、
その就職先や居住地について不可解な点があった
(ちなみに祖父は某有名フィルムメーカーの研究所勤務を経て某市の職員となっている)
訳ありで都会から逃げてきた若者の面倒を見る
何となく想像ができる
父から以前聞いた話によれば、
「俺みたいな境遇の若者が何人かいて、寝起きを共にしていた
面倒を見てくれていた親方の娘さんに気に入られていたが、俺は相手にしなかった」
(飲み歩いて帰ってくると、ネグリジェ姿で出迎えてくれたそうだ)
今思えば、父なりの考えがあり、そこの娘さんとはいい仲になってはいけないと思っていたのだろう
私も小さい頃は、そのお世話になった方への年始の挨拶に、毎年連れて行かれた
当時の市役所近くの大きい事務所
広い部屋に大きなテーブル
その部屋がぎゅうぎゅうになるほどの人々
幼かった私は当時は何とも思わなかったけれど、もしかしたらそういうところだったのかもしれない
(現在では、ストビューで見たところ建物の跡形すらなかった)
そんな父は母と一緒になった
世の子供達が必ず一度はやるアノ質問を私も両親に投げかけたことがある
「ねぇ、なんで二人は結婚したの?」
その時の父の回答
普段通りピースを吸いながら、視線をTVから少しも動かさずこう言った
「誰も貰ってくれる人がいなかったのさ」
子供心なりに
「これは聞いてはいけない話だったのか」
と思い、それ以上の事は聞かなかった、いや、聞けなかった
そして私もそれなりに歳をとり家族を持った
細かいこと、欲を言うとキリがないのだろうが、良いパートナーに恵まれたと言うべきだろう
むしろ上記のようなバックグラウンドを持つ私のパートナーということは、
相当な貧乏クジを引かせたと言わざるを得ない気もするが
彼女は、自身の経験から「先祖を大切にする」という考え方を持っていて、
「先祖は、その子孫に、自分のことを知ってもらうということを喜ぶ」
ということを良く言っている
私はその辺りはよくわからないので「そういうものなのね」程度の認識しかないが、
自身の先祖を知ることについては何ら不都合などはないと考えている
最も、上記のように、父方は厳密に言えば血が繋がっていないということになるのだろうが、
当時のあれやこれやを思えば、特段珍しいことでもなかったのだろうと考えている
そんな流れもあってか
また母方の祖母の33回忌が先日あったということもあってか
母方の先祖のことについて知る機会があった
正しくいうと、我がパートナーが
「先祖は、その子孫に・・・」
ってやつで、戸籍を可能な限り遡って整理したいということになり、
以前から私の母に話を持ちかけていたらしい
初めは母にやんわりと拒否されていたということだが
最終的には母が折れたということなのだろう、引き出しの奥から古い資料を引っ張り出してきてくれた
この資料収集と整理は、どうやら父の生前の仕事だったらしい
(父は行政書士というわけでもないのに、なぜかこういうのにはやたら詳しかったんだよね)
昔の戸籍謄本なので、手書きだったり、表現が昔風だったり
「朔日」って言葉、初めて知りました
(太陰暦での1日を指すそうです)
読めない箇所もいくつかあったらしいが、それでもほとんどの部分は読めたそうだ
実際には私の母方の祖母から遡り、江戸時代頃(と言っていた気がする)までの記録が残っていたとのこと
資料自体に直接アクセスしていたのは我がパートナーだけなので、詳しいことは私にはわからない
私自身は同じ部屋にいたが、やや離れた位置にいたため、資料を読んで手を動かしているなぁくらいにしか見えていない
そんな中、資料を見ている彼女と私の母との会話の中で
「認知・・・」
「これは私が墓まで持っていく・・・」
なんて言葉が聞こえた時があった
認知という単語から推定されることがあるが、おそらくそういう方がいらっしゃったのだろう
また、人には知られたくない秘密の一つや二つくらいあっても不思議はないので、
会話の中でそういう単語が出ても不思議はないだろう
そんなふうに思って、さして気にもしていなかった
それからしばらく経ったある日のこと
別件にて我がパートナーとの会話の中、この話が出てきた
彼女は相当に悩んだらしいが、私に対して口を開いた
「(私の母方の祖母は)正妻との子ではなかった
(私の母は)離婚歴があり、私の父とは再婚だ」
一応断っておくが、無理やり口を割らせたわけではない
これを聞いた時、母方の祖母の足取りの不可解な部分がわかった気がした
私の祖母は、某お米と日本酒の有名な県の出身と聞いていた
実際、私が小学校の低学年の頃、祖母と二人きりで新幹線で彼の地に旅行に行ったことがあり、
その時泊めてもらった家は、祖母の親戚の家だと聞かされていた
ニコニコと愛想の良いおばさんと、無口だけれどそっと見守ってくれるような優しさのあるおじさんの家で一晩眠りについたのをうっすらと覚えている
余談だが、そのおじさんは、私が大学生になるときに、大学から求められた保証人にもなってくれた
署名をいただくときに、私の父が、
「おじさん、お願いします」
と言って頭を下げていたのを覚えている
おじさんは無言で署名してくださった
そんな祖母は、夫を戦地で亡くしている
(海上での戦死という事で骨は帰ってきていない)
ちょうど母が生まれたのとほぼ同時に訃報が届いたとのことだ
祖母から送った最後の手紙には、生まれてくる子供(私の母)の名前についての相談があったとの事だが、
その返事が返ってくることはなかったそうだ
そんな祖母は、なぜ一人娘を連れて県外へ出たのか?
また、以前聞いたところによると、母が疎開していた頃、祖母は時々会いにきていたらしいが、 どうやら自分自身が母親だということは隠していたらしい
ある時母は、疎開先の大人たちに、時々会いにくる謎の女性について聞いたらしい
「あの綺麗な人は誰?
なぜ私に会いにくるの?」
後になって母が祖母から聞いたという話では、
「あの一言があったから、このままじゃいけないと思ってあなたを連れ出したのよ」
と言われたそうだ
ここからは私の推測になるが、
・祖母自身の出自ため、元のあった場所にいることができなかった
・その子である母も居場所がなかった(もしくは著しく限られていた)
・何らかの理由により母娘が共に暮らすことを許されなかった
以前母から聞いた昔話の中で、こういうのがあった
「あの時はね、雪で真っ白な中を、おばあちゃん(私の祖母)と一緒に歩いていたの
そう、たった二人で何時間もね
ただただ寒くて、凍えて、手足は霜焼けになって
それでも黙って歩くしかなかったんだ」
いつ頃の話かはわからない(忘れてしまった)が、おそらく疎開先から母を連れ出した後のことだろう
雪で真っ白というのも、祖母の出身県、また母を連れた祖母がたどり着いた場所(現在の母の居住地)とも整合性がある
祖母が母を連れてたどり着いた場所、現在の母の居住地は、
今では寂れてしまったものの、往時は割と有名な観光地として名を馳せていた場所である
そんな地の役所の目の前で、祖母は食堂を営んでいた
食堂といっても、役所の台所のようなもので、
営業時間は今で言うところのランチタイムのみ
メニューも天ぷらうどんのみという、かなりこだわった(?)ものだった
私自身の記憶の中に、こんな風景がある
平日の昼になると、目の前の役所からたくさんの人が流れ込んできて部屋が満杯になる
皆が天ぷらうどんをお腹に納めたのち、花札大会が始まる
昼休みが終わる頃になると満杯だった部屋がスッと空になり、花札や座布団は綺麗に片付けられていた
ひと段落した祖母が定位置に座り、エコーに火をつける
そんな祖母の横で、幼い私はバヤリース(もちろん瓶入り)のオレンジを飲む
一服した後、祖母が私に話しかける
「ボク(私の事)、ハンバーグ食べるかい?」
幼い私はウンと頷く
祖母は冷凍庫から手作りのハンバーグを取り出し、電子レンジ(当時の一般家庭にはないもの)で温めて私に出す
祖母の手作りのハンバーグ
冷凍したせいか、ちょっとボソッとした感じのある一口サイズのハンバーグ
ケチャップをちょこんと乗せて出してもらったっけ
そんな環境で祖母は母を女手一つで育て上げた
母から聞くところによると、相当厳しく躾けられたらしい
その中でも私の中に残っているエピソードをいくつか
ある時(おそらく進学などの節目の時)祖母は母にこう言ったそうだ
「その長い髪を自分で結べないのなら切りなさい」
母は必死になって鏡台に向かい三つ編みの練習をしたそうだ
また進学で親元を離れる時には、祖母の目の前で、潰れるまで酒を飲まされたそうだ
おそらく女性の一人暮らしを警戒して、祖母自身の目の届くうちに経験を積ませたのだろう
母はそれ以来、アルコールはダメになったそうだ
また外食メニューについても指定があったらしい
一人暮らしではとにかく野菜が不足するから、必ず「タンメン」を食べるよう言われていたとか
これも祖母から母への愛の形の一つなんだろうと思う
そんな母も、ある資格を手にして社会に出る
その後何があったかは知らないが、父と出会い一緒になった
新婚当初は祖母の家を二世帯住宅に改修し3人で住んでいたらしいが、
色々あり、最終的にはそこを出て、父と母は別の場所に居を構える
小さい頃に聞いた記憶では、父と祖母の折り合いがうまくいかなかったらしい
まぁ、あのちゃらんぽらんな父ならば、あの厳格な祖母とぶつかるのも当たり前だろうなぁと幼心に納得したものだ
そして私が生まれる
この時代には珍しく、高齢出産だった(母31歳)
と、ここまでの母の辿った道で不可解な点がある
おそらく「母の」と言うよりは「母と祖母の」と表現したほうが適切かもしれない
「なぜあんなにも厳格だった祖母が、あの訳ありの父との結婚を許したのか
その疑問が氷解した
簡単な事だった
「母も訳ありだったのだ」
当時のことを考えれば納得のいく話だ Xがついた出戻りをもらってくれるのならば、相手が訳ありでも目を瞑ろうということだろう
高齢出産というのも頷ける
が、ここで一つ疑問が残る
母の子は、私だけなのだろうか?
母は私を31歳で産んだというのは事実だが、それ以前に出産経験があるかどうかは本人しか知らない
いや、今となってはわかる人が残っていない
父は知っていたのだろうか、それすらも今となってはもうわからない
仮に私に兄姉が存在したとしよう
現時点で私が知り得る範囲での戸籍情報に存在しないということは、
母が離婚した時点で、その親権はその当時の夫が持ったということになる
となると、私が真実を確かめる術はない
可能性だけ考えれば、ゼロではない
そんなフィクションみたいな胸熱展開が私の人生にあるかと考えるとなかなか複雑な心境になる
養子の系統
妾の系統
それぞれが繋がって私はここにいる
ならばこれから私が繋いでゆくのは何だろう
そんなことをぼんやりと考える

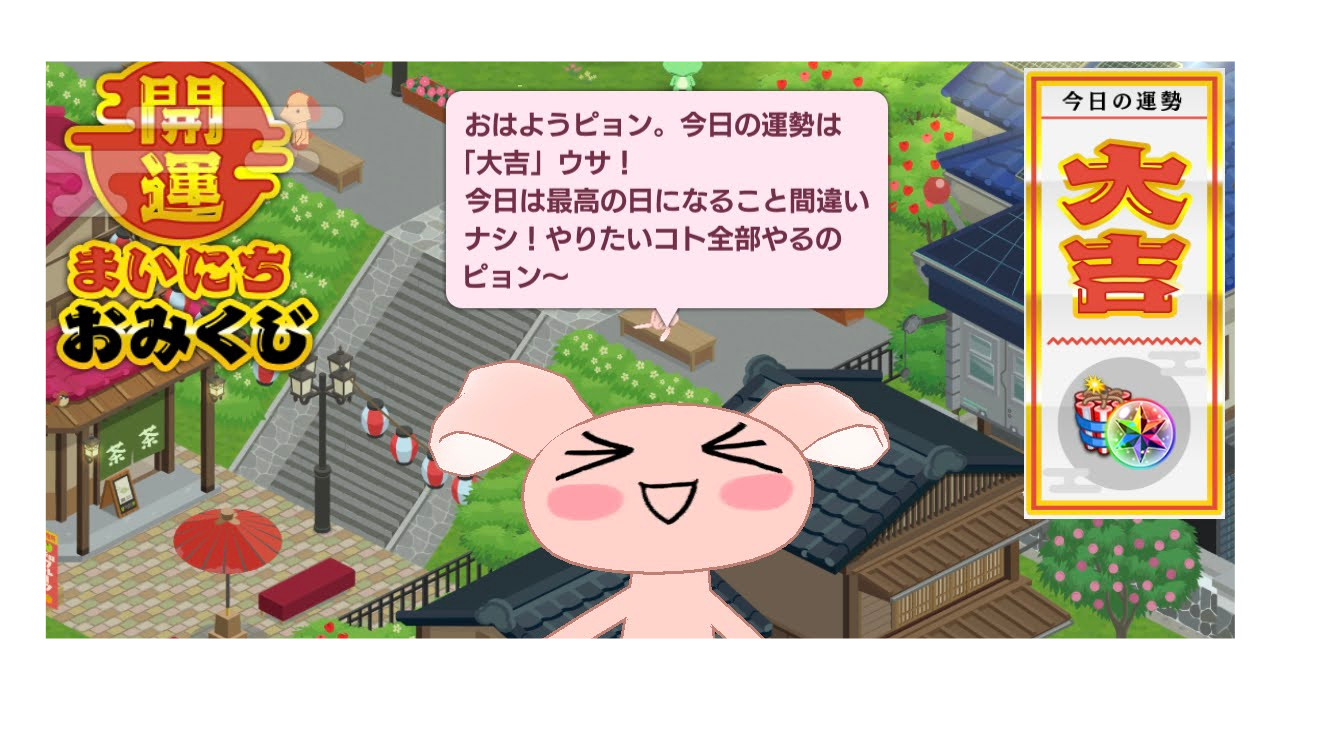
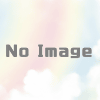
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません